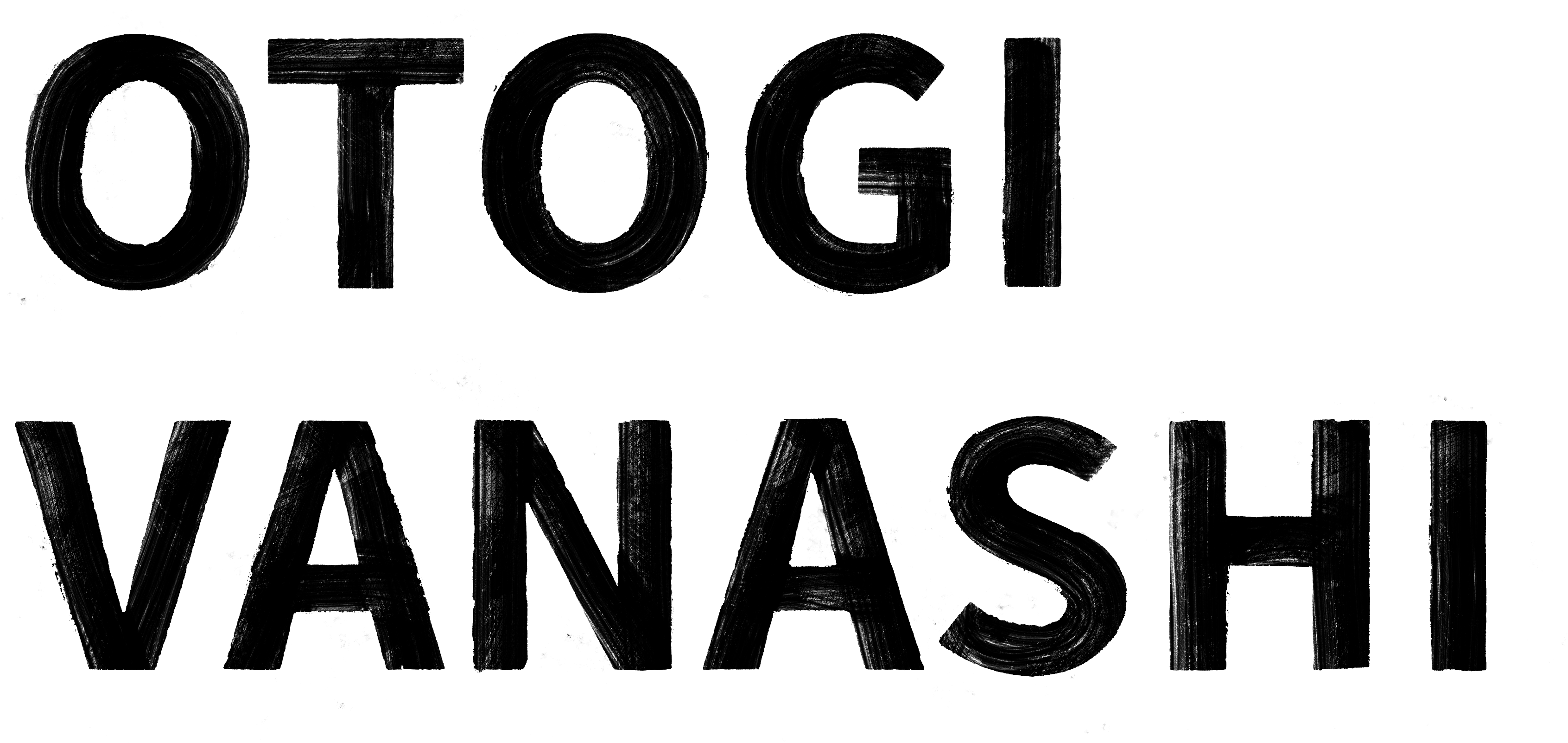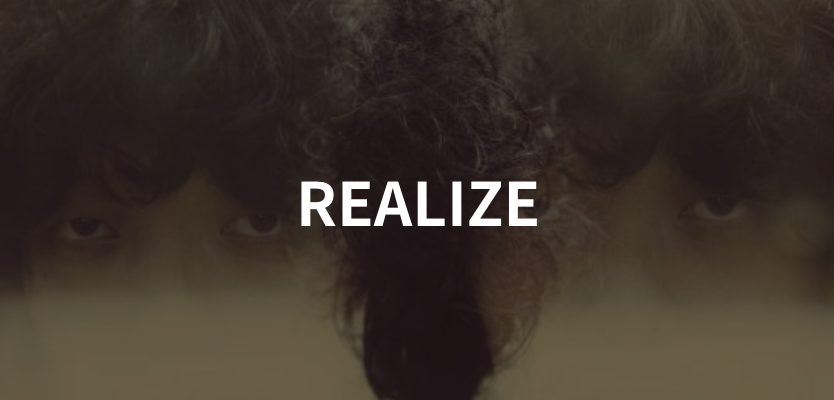2022年8月13日(土)に開催を控えている、東京・日比谷野外大音楽堂でのおとぎ話のワンマンライヴ〈OUR VISION〉。ライヴに先駆けて6月22日にはニューアルバム『US』がリリースされたが、同公演に向けた本連載では、フロントマンの有馬和樹に、『US』の前に発表してきた11枚のアルバムを1作ずつ語ってもらう。
第8弾となる今回は、2016年10月に発表された8作目『ISLAY』について。『CULTURE CLUB』に引き続きfelicityからのリリースで、吉田仁との共同プロデュースとなった同作。軽やかで躍動的なアンサンブルと端正なプロダクションに前作からの連続性を感じさせつつ、テーム・インパラ以降とでも言うべきサイケデリアが聴き手を色鮮やかなトリップへと誘う。作詞の面においても〈自分が書いてきたテーマがなんだったのか、ようやくはっきりしてきた〉という有馬がこの時期、見つめていたものとは?
Interview & Text by 田中亮太
ISLAY
ーー『CULTURE CLUB』がリリースされたあとのバンドの状況は?
「『CULTURE CLUB』を完成した時点で、バンドとしてもひとつの季節が終わったから、メンバー間で喧嘩するとかがまったくなくなったわけ。だからモードとしては、大きい音を出すのがひたすらに楽しい、バンドっていいなというものだった。『ISLAY』を作るときも、ただただ楽しいって感じだったな」
ーーこの頃から〈おとぎ話を慕っている〉と公言しているバンドとの対バンなどが増えたように思います。
「増えた。それもあって認めてくれる人がこんなにいたんだと思えたし、好きにやっていいんだという後押しにもなったよ。『THE WORLD』くらいまでは対バンとかめっちゃ断っていたもん。だけど、『CULTURE CLUB』が出来てからは、楽しいからなんでも出ている」

ーーこれまで一作ごとに話を聞いてきて、ひとつ前の作品のカウンターとして次の作品を作ってきたことが多いと思ったんですけど、『ISLAY』には『CULTURE CLUB』からの連続性が感じられます。
「地続きになているよね。どっちも、ひたすら才能のあるロックバンドがひたすらいい曲をやっている、という感じ。おとぎ話というバンドとしてのサウンドが作れているんだよね」
ーー前作のどんなところをさらに発展させようとしたんですか?
「ここらへんでブロンディーとかを聴き出すんだよね。そういう80年代の音楽を掘るのがむっちゃ楽しくなってきちゃった。“YUME”という曲はカーズを意識していたり」
ーーなるほど。確かにアルバム全体を通して、70年代後半から80年代前半のCBGB感が出ている印象です。ブロンディーもいればラモーンズもいればトーキング・ヘッズもいるみたいな。
「ホントにそんな感じ。あとフィーリーズとかね」
ーー僕は『ISLAY』にロック以前のオールディーズやロックンロールっぽさを感じていたんですけど、それも当然だったんですね。80年代はバックトゥ50sの時代でもあったわけで。
「うんうん。バンドの力が上がったことで、作りたいものを作れるようになったんだよね。“セレナーデ”はサザンオールスターズみたいな曲をやろうと作ったし、1曲目の“JEALOUS LOVE”はブラーの“Girls & Boys”じゃないけど、ブラーが急に打ち込みをやっちゃった感じで作ろうとか、そういう感じだった。で、ブラーだったら2曲目は絶対歪むよね、ということで“ブルーに殺された夢”を作って。バンドとしては幸せな季節で、モチーフにはことかかない時期だった。ただ笑いながら、楽しく作っている感じだったな」
ーーそれにしても80年代の音楽を有馬くんが発見していった背景はなんだったんでしょう?
「楽しいほうがいいじゃん、と思えたからかな。バンドをやることに苦しい期間が続いていたけど、それがやっと終わったから。ここらへんでカジ(ヒデキ)さんのバックバンドをやるようになったり、先輩ミュージシャンとの親交も増えてきたんだよね。そこで、〈有馬くんの曲ってあれに似てるよね〉と教えてくれることが多くて、自分の周りにいる人たちとキャッチボールできるようになった。本当にただ〈音楽〉という感じになってきたかな。バンドの初期はビートルズっぽいとかそういうことにこだわっていたもんね。ここらへんからなんのこだわりもなくなった」
ーーあと『ISLAY』はサイケデリックな側面もよく出ている作品ですよね。
「普通にやっていたらそうなった、という感じ。テーム・インパラとかも好きだし、〈やっぱりおとぎ話はU.F.O. CLUBのバンドなんだよね〉というのはみんなで話していたな。あと、クリトリック・リスのスギムさんがこのアルバムを聴いて感想を言ってくれたんだよね。〈おとぎ話は『CULTURE CLUB』で『Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band』を作ったと思ったら、次のアルバムで『Revolver』を作りやがった〉言ってくれて、この人はわかっているなと思ったよ(笑)」
ーー歌詞に目を向けると、このアルバムはあえて言葉に重みを持たせていないように感じました。
「そうだね。もともとストックがあった歌詞もかなり変えた。いまの自分やいまの時代性をふまえて、どういうことを歌うべきかを考えはじめた時期だった」
ーーいまの自分と時代性をふまえて何を歌おうと思っていた?
「ジェンダーフリーというか、世の中が性別の固定観念から自由になろうとしているし、性の多様性に寛容になってきたよね。僕もそっちのほうががいいし、もともと男はこうあるべき/女はこうあるべきみたいな考えがすごく嫌い。もっとラクでいいのになと思っていたなかで、世界もそうなっていったんだよね」
ーー僕は『ISLAY』にはバンドのアティチュードを歌った歌詞が多いというふうに思っていたんですが、むしろバンドという枠組みも超えて、有馬くんにとっての共同体のあり方の理想像みたいなことを歌っているんでしょうね。
「それはめちゃくちゃ言い得ているよ。いまはじめてそれを言語化してもらえたと思う。この時期からの自分の大きなテーマになっていて、新作の『US』でそれをちゃんと作品にできた感じ」
ーー『ISLAY』は『US』に向かう第一歩でもあったと。
「自分の目の前にいるお客さんには男の人も女の人もいるじゃん。バンドのシーンにはたまに〈男の客がいないバンドはよくない〉とか言う人がいるけど、そういう考えは本当に嫌い。無理。〈有馬は女の人のために歌っているよ〉とうそぶいて言いたくなるけど、性別なんか関係なくやっているよ。男だけど別にカッコつけてないし、可愛いと言われたら嬉しい。男女がどうかは関係ないわけで、そういう多様性を認めない人がなぜいるんだろう?と思うよね。そういうことをよく考えるようになっていった」
ーーそのきっかけには何かあったんですか?
「結婚したことかな。自分が経験してみてわかったのが、結婚って特に日本だと古い男性観/女性観に基づいたものになっているんだよね。その、かくあるべしみたいなのに自分も縛られて息苦しくなっていた」
ーー有馬くん自身が社会化されたジェンダーロールに苦しめられたという経験があったんでしょうね。
「そうそう。いまとなってようやくその答えが見えてきた感じ。とにかく、生きづらいという感覚だったんだよね」
ーーじゃあ『ISLAY』から1曲選ぶとすれば?
「“JEALOUS LOVE”かな。すごく自由なんだよね。自分でも〈おとぎ話ってここにきてこんな曲を作るんだー〉と思えた。仁さんとダンスチューンを作っちゃえと話して、ディスコに向かった感じ。結構難しい曲なのに、みんなで笑いながら作ったのもすごく良かったな。これ、3パターンくらいアレンジを考えたんだけど、いちばんダサいものを採用した。出来たものはかっこいいんだけどね。音楽ファンが作った曲という感じだな」
おとぎ話<OUR VISION>
2022年8月13 日(土)
東京都 日比谷野外大音楽堂
開場 16:00/開演 17:00
チケット:全席指定 ¥6,600(税込)
お問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:03-5720-9999