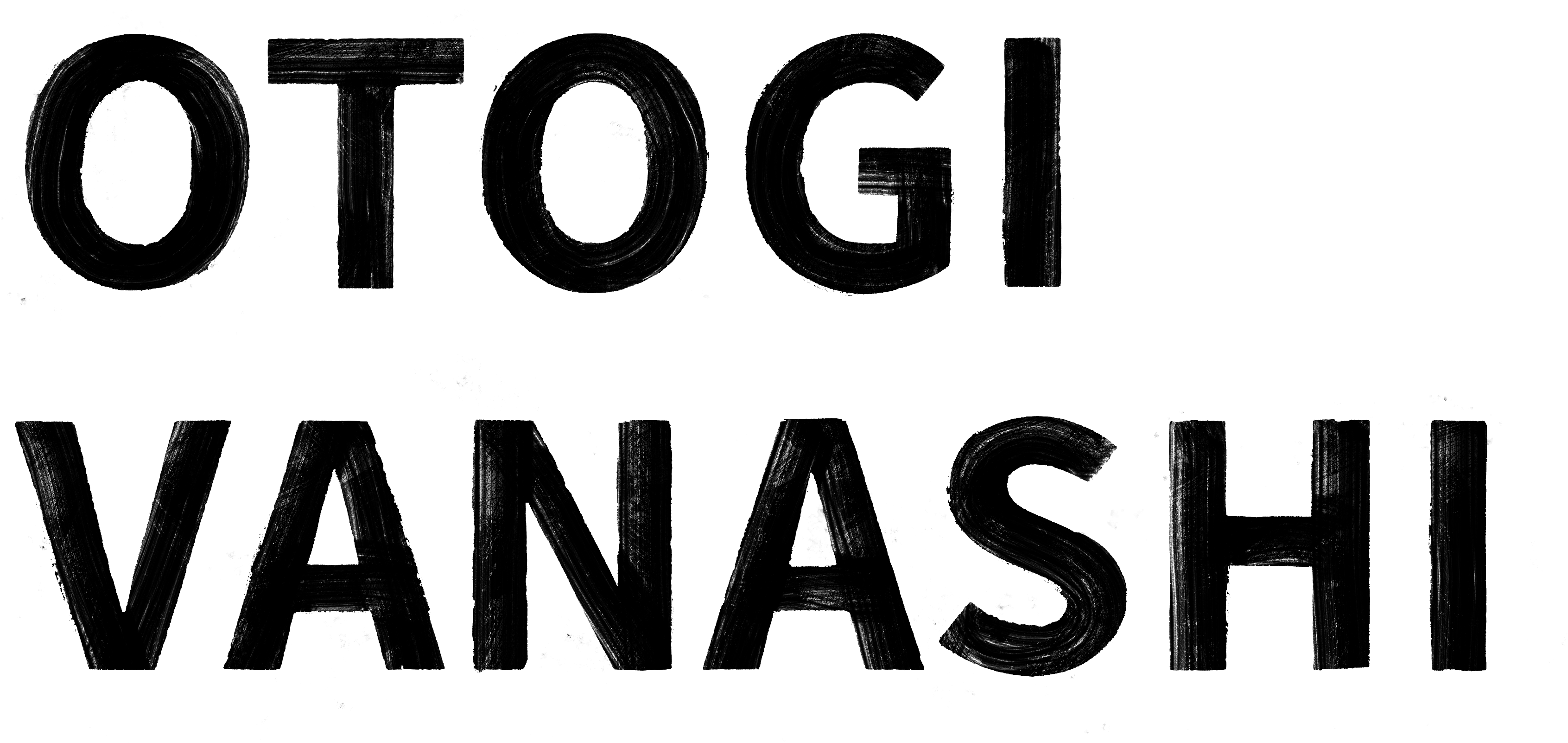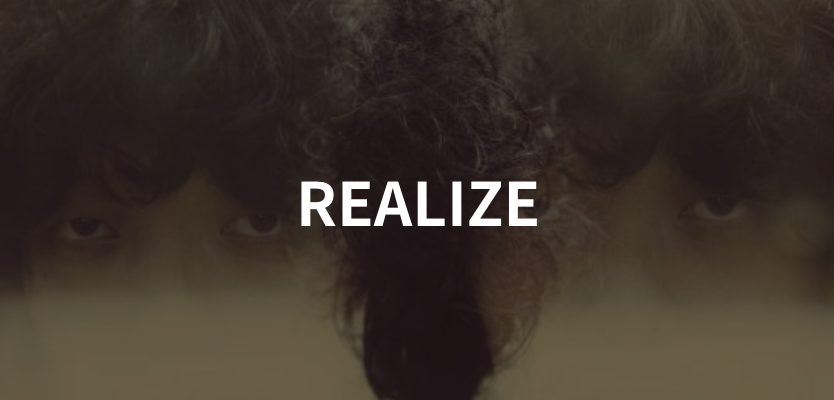2022年8月13日(土)に開催を控えている、東京・日比谷野外大音楽堂でのおとぎ話のワンマンライヴ〈OUR VISION〉。ライヴに先駆けて6月22日にはニューアルバム『US』がリリースされたが、同公演に向けた本連載では、フロントマンの有馬和樹に、『US』の前に発表してきた11枚のアルバムを1作ずつ語ってもらう。
第9弾となる今回は、2018年6月に発表された9作目『眺め』について。吉田仁との共同プロデュース3作目にして現時点での最終章にあたるこのアルバムでは、前2作で磨きをかけた無駄のないアンサンブルにさらなる艶を加えつつ、ネオアコースティック〜シューゲイザーなサウンドによって独特の浮遊感が醸されている。また、いくつかの楽曲において、以降の作品を予見するかのようなブラックミュージック的なグルーヴが出ていることも見逃せない。人種差別や性差別など現代が抱えてきた多くの問題が可視化され、アート側からも変化に向けて社会へとコミットメントしようとする動きが活発となった『眺め』の時代、有馬はどういうことを考えていたのか。
Interview & Text by 田中亮太
眺め
ーー『CULTURE CLUB』と『ISLAY』というfelicity からの2作を経て、バンドのコンディションはどんな感じでした?
「めちゃくちゃいい感じだったよ。写真をずっと撮ってくれているカメラマンのタイコウ(クニヨシ)さんは以前から〈おとぎ話は何十年と続けられるチケットを持っているバンドだから〉と言ってくれていたんだけど、それを自分たちでも少しずつわかりはじめていた。前の2作で、自分たちはこういう表現でこういうふうにやり続ければいいんだ、という感覚を掴めたんだよね。売れなきゃいけないみたいな強迫観念から解き放たれたというか、自分たちが何をしようが音楽シーンは移ろいでいくし、そこに迎合しようが文句を言おうが何も変わらないということに気付いて、おとぎ話としての音楽を追求するほうにひたすら向かった。充実したバンド活動ができていた、という感じかな」

ーー前2作の内容に手応えを感じられていたこともバンドを後押ししたんでしょうね。
「そうだね。それはデカかった。『CULTURE CLUB』というアルバムは、それまでのバンドの活動のなかではじめて、まっとうな評価を得た気がしたんだよね。これを皆がちゃんと好きだと言ってくれるのなら、もう別にいいやと思えた。そこから自分たちが作りたいものを楽しんで作ることにスイッチして、その結果出来上がったのが『ISLAY』。『眺め』はその単純な延長線上だったかな。アルバムのジャケットに関しても、それまでは絶対に4人で写っていないといけないと思っていたんだけど、今回はじめて有馬1人の写真にしたんだよね。そういう〈バンドとはかくあるべし〉みたいな固定観念からも解き離れたし、とにかく楽しいほうがいいなと思えたんだ」
ーー『ISLAY』では80年代のポップに接近したと言われていましたけど、『眺め』の制作時はどういう音楽から刺激を受けていたんですか?
「どうだったっけな。『眺め』はどこかに当てはめるというよりは、自分たちの持っているポテンシャルをそのまま出したという感じかも。リファレンスがある曲もあるけれどね。たとえば“HEAD”という曲は、アーケイド・ファイアがジェームズ・マーフィのプロデュースで作ったアルバム(『Reflektor』)を意識していたし」
ーー新作『US』のリードソングだった“FALLING”について話してもらったときに、〈『眺め』の制作時点で、従来のロックンロールの演奏には飽きていて〉と話されていたじゃないですか。『眺め』はそこから脱却しようとした最初の一歩でもある?
「そうだね。脱却しようとした結果、逆説的にそれまでやってきたことを全部やりきったという感じ。いままでの経験のすべてを『眺め』に注ぎ込むことができた。しかも、いい塩梅でやれたんだよね」
ーー確かに『眺め』のアンサンブルはとても端正で無駄のない印象です。あと、このアルバムの時点でブラックミュージックのフィーリングも少し出てきていますよね。
「昔、父ちゃんの影響で聴いていたモータウンやオールディーズのビート感をはじめて出した作品だと思う。もともと有馬はPファンクとかが超好きだったから、自分たちの音楽にもそういう要素を入れたかったんだけど、やっぱりこの4人では黒さは出ないんだよね(笑)。でも、出ないなりに出そうとがんばっているバンド特有の魅力ってあるじゃない? おとぎ話はそこをめざしている。これくらいの時期は、本当にブラックミュージックがおもしろかったと思うし、有馬にはロックバンドだからそれを無視していい、という考えはなかった。だから、トライ&エラーでやってみたし、どうやれるかをみんなで必死になって考えていた。でもね、おとぎ話は予想以上にロックだったよ(笑)。フルスペックのロックバンドだね」
ーーその一方でネオアコ感も出た作品になりましたよね。ただ、ネオアコ自体がブルーアイドソウルのインディー解釈という側面もあるわけで。
「だよね。アズテック・カメラとかね。そこにはfelicityに所属していたことも大きいと思う。もともとトラットリアが前身のレーベルだし、ボスの櫻木(景)さんは、ロックやアシッドジャズ、ダンスミュージックなどが並立に存在しているシーンのなかにいた人。そういう人たちと話しているなかで、自然と高校生のときに聴いていたスタイル・カウンシルとかを聴き直したりもしていた。それが音の感じにも出たんじゃないかな」
ーー 『眺め』のサウンドのキラキラした感じは、イギリスのプロデューサー、ジョン・レッキーが80年代終盤から90年代前半頃に手がけた作品に近いと思ったんですよ。ストーン・ローゼズのファーストやレディオヘッドのセカンドとか。
「『眺め』にあの時代の感じはあるよね。わかるわかる。そこは超意識していた。キャストのファーストとかもジョン・レッキーだよね。あのアルバムも最高」
ーー“ONLY LOVERS”あたりはリアル・エステイトとかネオアコの雰囲気を持ったUSインディーを彷彿とさせたり。
「そこらへんのUSインディーのバンドがまったくノれないディスコをやったりするじゃん? ああいうのは意識していたな」
ーー〈まったくノれないディスコ〉と言われたように、このアルバムの多くの楽曲は淡々と進むし、平熱の温度感を貫いていますよね。そうしたムードを求めた背景は?
「ここらへんからミュージシャンもInstagramとかで有名人と写真を撮ったりして〈いいね!〉を稼ぐみたいな感じになってきたじゃん? そういうものに対しての距離感がこういう形で出たんだよね。音楽って本来はひたすら美しいものなのに、なんだか汚されていっている気がして」
ーー音楽がセレブリティーカルチャーに呑み込まれていったというか。
「おとぎ話はこのアルバムでそこと完全に距離を置いた気がする。“素顔のままで”でもそいういうことを歌っているしね」
ーー“素顔のままで”では〈アーティスト気取ってる君には興味がない〉と歌っています。
「〈恋のうたうたってる君だけが好き〉ってね。みんな、なんでそんなに自分の居場所を示すことにこだわるんだろう?と思っていたな。逆に、おとぎ話は4人で音を出す、4人で演奏するというところに居場所を置いていたんだなと気付いたし、そうやっていままでやってきていたんだなと思うと、すごく愛おしい気持ちになった。だからこのバンドはすごく最高だな、と思えた」
ーー『眺め』の時期は、レイシズムやセクシズムの問題の多くの人が目を向けたときでもあって、社会をより生きやすいものにしていきたいというメッセージを投影された作品が増えていましたよね。そうした時流を有馬くんはどう見つめていましたか?
「自分もむちゃくちゃ刺激をもらっていたよ。たとえばグザヴィエ・ドランの映画とかを観てすごく感動したし。僕自身が〈男だったらこうするべき〉みたいな男性観とかけ離れている人間だから、古い固定観念が崩れていくことは自分の後押しにもなった。ひとりひとりが自分自身らしく生きていけるのがいいなって。ふまえて周囲のミュージシャンを見回したときに、自分の主観や正義のみを聴き手に押し付けるような人が多いなとも思ったんだよね。そこに居心地の悪さを感じていたということも『眺め』の歌詞を書いているときに気付いた。“ONLY LOVERS”の歌詞では、自分は平成生まれじゃないのに〈平成生まれの僕〉と歌ったり、それまで有馬の独白だった部分が本当に解き放たれたというか、表現として自由になった。なかでも“HOMEWORK”の〈毎日働いて〉というフレーズを書けたことは大きかった。やっとはじまった気がしたし、音楽ってこういうことを歌うべきだと思えたんだよね」
ーー『眺め』から1曲あげるとすれば“HOMEWORK”になります?
「そうだね。これはどのライヴでやっても〈かましているな〉という気がするんだよね。有無を言わさぬ怖い曲だと思うな(笑)」
おとぎ話<OUR VISION>
2022年8月13 日(土)
東京都 日比谷野外大音楽堂
開場 16:00/開演 17:00
チケット:全席指定 ¥6,600(税込)
お問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:03-5720-9999