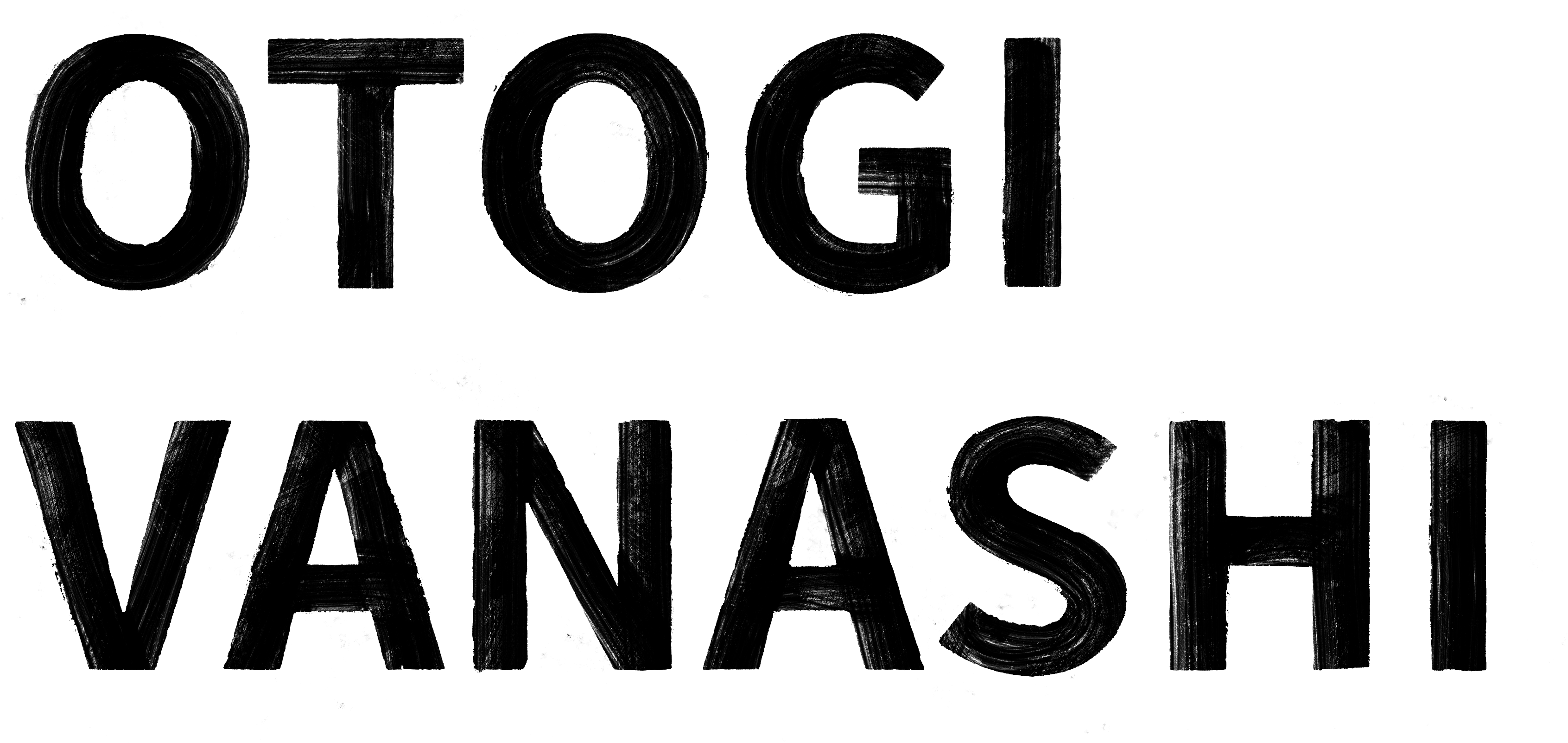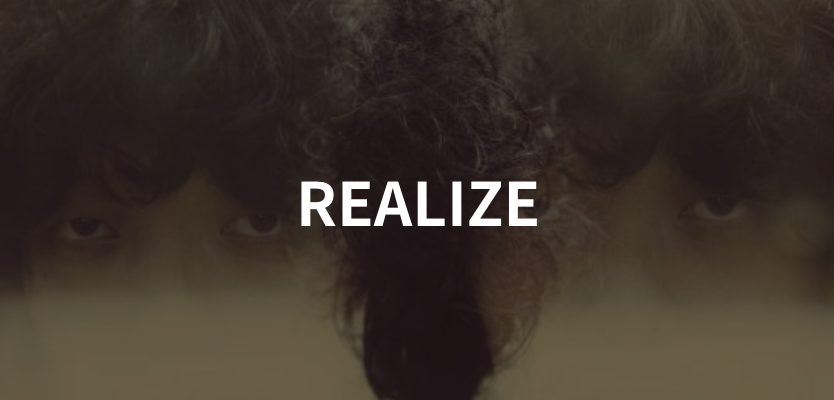2022年8月13日(土)に開催を控えている、東京・日比谷野外大音楽堂でのおとぎ話のワンマンライヴ〈OUR VISION〉。ライヴに先駆けて6月22日にはニューアルバム『US』がリリースされたが、同公演に向けた本連載では、フロントマンの有馬和樹に、『US』の前に発表してきた11枚のアルバムを1作ずつ語ってもらう。
第7弾となる今回は、2015年の1月にリリースされた7作目『CULTURE CLUB』について。前作『THE WORLD』をリリースしたあと、山戸結希監督の映画「おとぎ話みたい」で大きくフィーチャーされたバンドは、挿入歌となった新曲“COSMOS”を引っ提げてインディーの名門レーベル、felicityへと移籍。共同プロデューサーに吉田仁、アートディレクターに木村豊を招いた『CULTURE CLUB』は、持ち前の艶やかさやサイケデリックな感覚を残しつつ、よりソリッドでタイトになったサウンド(&アートワーク)でおとぎ話の新章を強く印象付けていた。気持ちも環境も心機一転となったこの時期、有馬は何を考えていたのだろう。
Interview & Text by 田中亮太
CULTURE CLUB
ーー『CULTURE CLUB』の話にいく前に映画「おとぎ話みたい」について訊かせてください。もともと山戸監督がおとぎ話のファンだったんですよね?
「そうそう。〈MOOSIC LAB〉という音楽と映画を融合したインディー映画の祭典があって、それに参加することになった山戸監督がおとぎ話に声をかけてくれたんだよね。それで、こっちからも〈じゃあ新曲の“COSMOS”を提供します〉と言ったんだ。『BIG BANG ATTACK』の時点で“COSMOS”の原型は出来ていたんだけど、ずっと出し渋ってはいたんだよね。あの曲はこれからの自分たちの名刺として出したくて」
ーーじゃあ、有馬くんとしても相当に手応えのある曲だったんですね。
「だいぶ手応えはあった。〈ひらり ひらり〉というあのコーラスは、それまで誰も書いていないと思ったんだよね。コーラスで切なくさせる、というのをちゃんとやれた曲だと思う」

ーー“COSMOS”は有馬くんの目論みどおりに、いまやバンドの代表曲となったわけですけど、この映画で話題になったという理解で正しいですか?
「映画を通じて、という感じかな。山戸監督には映画のリファレンス的なものとして、MVも撮ってもらったんだけど、それもすごく評価されたから。レオス・カラックスの作品みたいなとんでもない映像で、あのMVでさらに〈山戸結希はすごい才能なんだ〉と認知された感じだったよね」
ーーちなみに、有馬くんが作り手として山戸監督に近いと思えたところはあります?
「共感を覚えるところしかなかったよ。作品を作ることに対してのストイックさとかね。あと、もともと僕は男性性や男尊主義とかを忌み嫌うタイプの人間なんだけど、山戸監督が作品で描く女性の強さを観て、彼女がおとぎ話の曲を気に入ってくれたのは、曲に出てくるキャラクターがぜんぜんマッチョではなく、どっちの性別にもとれるからだったんじゃないかな、と思っていた。そう考えさせてくれたのは、自分にとって礎になった。“COSMOS”の歌詞も〈僕〉とか言ってないし、性別を限定しないようにはしているんだよね」
ーー『CULTURE CLUB』からレーベルがfelicityになったわけですけど、リリースが決まるまでの経緯を教えてください。
「『THE WORLD』を出したあとに牛尾(健太)がバンドをやるのが辛くなって失踪したんだよね。でも結果的に戻ってはきてくれて、そこで一度終わったおとぎ話が復活したんだよね。そのタイミングでブラーの武道館公演があったんだけど、牛尾がチケットを取ってくれて、4人で行ったんだよ。ホントに4人で並んで九段下の駅から日本武道館までを歩いて(笑)。で、開演前に〈またがんばろうぜ〉みたいな話をしていたら、武道館に(felicityのボスの)櫻木景さんがいたの。で、僕が〈おとぎ話、もう一回旗を揚げたいんでfelicityで出してもらえませんか?〉と櫻木さんに頭を下げた」
ーー有馬くんと櫻木さんは当時から交流があったんですか?
「えーっとね、一応顔見知りではあった。THE BITEを通じてかな。(felicityからリリースしていた)THE BITEとおとぎ話とでスプリットを作ろうみたいな話があって、そこで繋がっていたんだよね。そのリリースは結局流れちゃったんだけど」
ーーfelicityから出したいと思った理由は?
「それまでのおとぎ話は『THE WORLD』で清算したから、今回が新たなスタートとなるわけ。そこで〈日本のいちばんかっこいいレーベルはなんだろう?〉と考えたとき、felicityだと思ったんだよね。櫻木さんは、売れる曲/売れない曲みたいな感じで、音楽を判断しない。バンドがやりたいことがたとえインストだけのアルバムだとしても、おもしろいねと言ってくれる人。音楽に愛のある、カタログに愛のある人で、話してみてすごく感動したんだ。その一方でポップじゃないといけないということもわかっている人で」
ーー『CULTURE CLUB』以降の3作は、SALON MUSICの吉田仁さんを共同プロデューサーに招いています。彼とやってみていかがでしたか?
「仁さんは、〈この曲はこういう感じでやりたいんです〉と言ったことをすぐに理解してくれるんだよね。〈これ、実はベイ・シティ・ローラーズのつもりで作ったんですよ〉と言ったら、すぐにわかってくれたし、そういうツーカー感はそれまであんまりなかった。調べるまでもなく知っていて伝わる人ってなかなかいないんだよね」
ーー『CULTURE CLUB』は色気のあるオールドロックと現代的なプロダクションの間でうまく舵取りのできた作品という印象です。どういうサウンドをめざしていたのでしょう?
「テーム・インパラとかディアハンターの話をよくしていたね。自分たちのサイケな部分とかをもう隠そうとせずに曝け出していいなと思っていた。あとハイムだ。ハイムのアルバムにはめちゃくちゃ刺激を受けたよ」
ーー確かにハイムは納得です。
「“告白ジャム”って打ち込みを入れた曲とかに顕著に表れているけど、ハイムの可愛さ、可愛いけどロックみたいな感じにはすごく憧れた。それって結構おとぎ話の魅力でもあるから。あとフェニックスもすごく聴いていた。ハイムとフェニックスはかなり大きいね」
ーー『CULTURE CLUB』の音域ごとに分離がはっきりしていて、メリハリのある音作りに、そういったバンドとの同時代性を感じます。ただ、ポップシーン全体を見回すと、この2015 年くらいからロックバンドが存在感を示すことが難しくなってきた時代に入ってきたとも言えますよね。
「徐々にそうなってきたよね。ラップとかがどんどんおもしろくなって」
ーーこのアルバムの“少年”でも〈ロックンロールバンド もう時代遅れになってしまっても〉歌われていて。
「〈ブリットポップは死んだ〉みたいな気持ちだったんだよね。だけど、俺はロックンロールをやるぜ、という感じだったかな。レニー・クラヴィツがロックンロール・イズ・デッドと言っても、誰も文句言わないじゃん」
ーーあっけらかんとした気持ちで歌えていたと。歌詞の面ではどういう意識で取り組まれていたんですか?
「このあたりから本当の自分探しがはじまった気がする。このアルバム、わりといろいろなことを歌っているんだよね。基本的には恋の歌が多いんだけど、人を好きになるという感情についてより踏み込んで書くようになった。それに加えて笑える歌もあるし、相変わらず少年ジャンプ感を持った曲もある。そういうのがぜんぶ同居しつつ、作詞家としては次の一歩を歩みはじめたアルバムだと思う。これ以降はその流れでどんどん思考を深めつつ、新作の『US』で本当に自分が歌いたいことをやっと見つけたという感じかな」
ーーじゃあ『CULTURE CLUB』は模索ではないけど、いくつか試行錯誤していた面もあったんでしょうね。
「そうだね。『THE WORLD』で一回青春が終わったから、そこから大人になろうとしているという感じかな。7枚目のアルバムなのに荒削りな部分もあるというのはそれが理由だろうね」
ーー『CULTURE CLUB』から1曲選ぶとすれば?
「やっぱり“COSMOS”になるね」
ーー“COSMOS”について、自分は終わった恋についての歌だと解釈しているんですけど、一聴わかりやすい曲ではないと思うんです。歌詞もすごく詩的だし、楽曲の構造自体も掴みどころがないし。
「超抽象的だよね」
ーーそういう曲が、なぜリスナーからここまで支持されたんだと思います?
「これはね、まだ謎。いまだにわからない。ロックンロールのカタルシスがあるかというと別にないんだよね。焦燥感みたいなものがあるわけでもないし。不思議なんだよね」
おとぎ話<OUR VISION>
2022年8月13 日(土)
東京都 日比谷野外大音楽堂
開場 16:00/開演 17:00
チケット:全席指定 ¥6,600(税込)
お問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:03-5720-9999