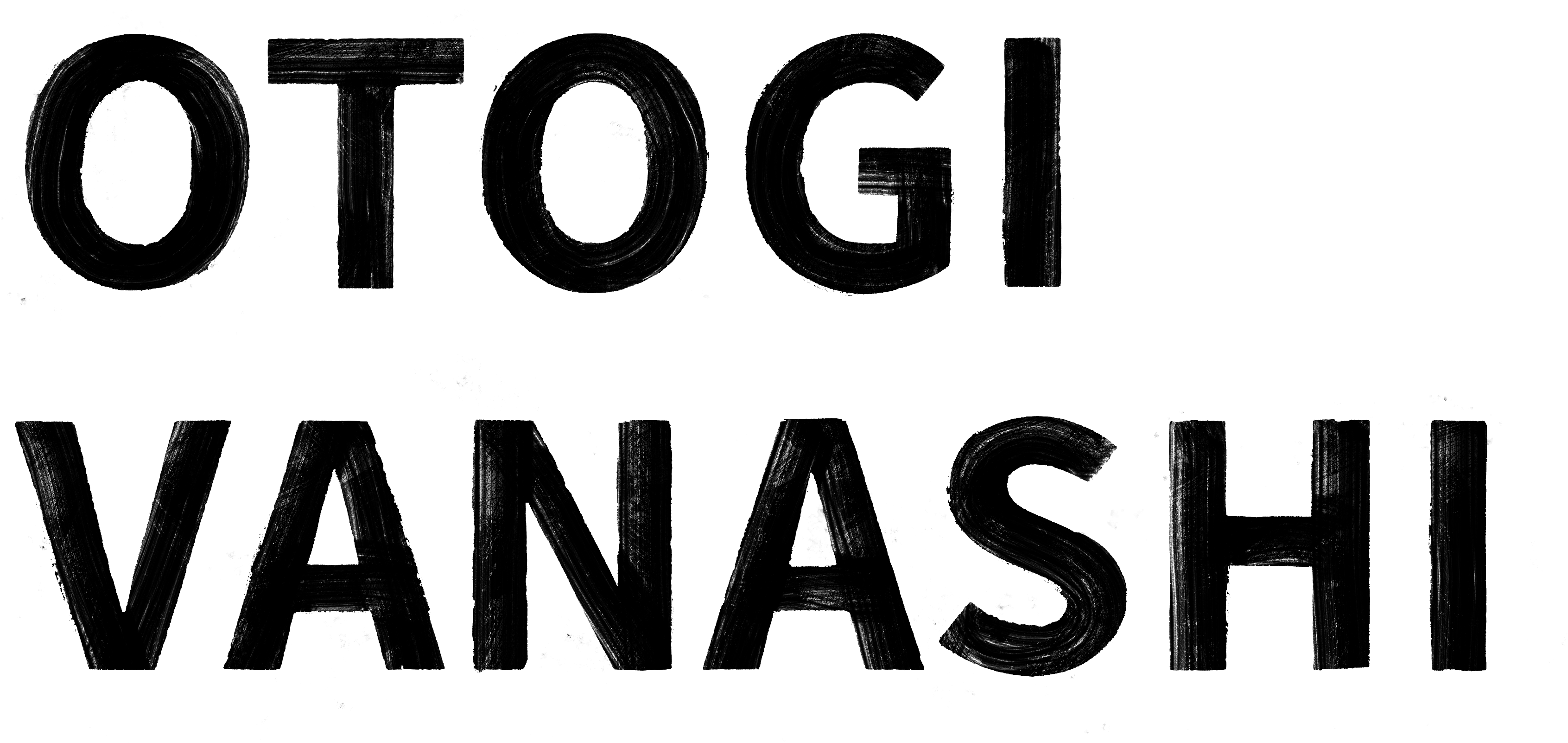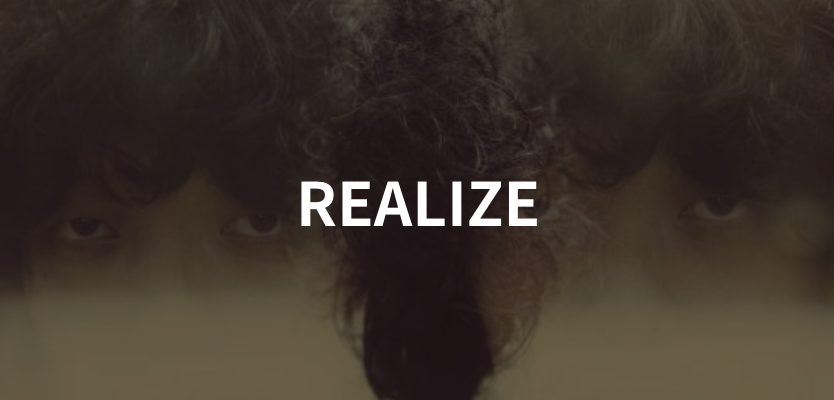2022年8月13日(土)に開催を控えている、東京・日比谷野外大音楽堂でのおとぎ話のワンマンライヴ〈OUR VISION〉。同公演に向け、バンドがこれまでに出してきた11枚のアルバムを1作ずつ振り返ってもらおうというのが、今回からスタートする「HISTORY OF O.V.」の主旨だ。
はじめにことわりを入れておくと、フロントマンの有馬和樹を含む3人のメンバーと同年齢である筆者は、これまで彼らを熱心に追ってきた人間ではない。もちろん、折につれ音源を聴いたり、ライヴを観たりすることはあり、その度に不世出のロックバンドたることは認識していたわけだが、どこか距離を置いて彼らを見ていたことも事実だ。しかしながら、2020年のアルバム『REALIZE』の素晴らしさに感銘を受け、かつ有馬たちと同じく40歳という人生の節目を昨年迎えたことで、そろそろ〈日本のロックンロール最大の謎!〉と称されるこのバンドに向き合い、彼らを解いてみたいと考えた。はたしてその謎は解明されるのか? このインタビュー連載には、その苦闘の跡が刻まれることだろう。この1回目は2007年9月にリリースされたファーストアルバム『SALE!』について、といく前に6月22日に発売をされたばかりの新作『US』からのリードソング“FALLING”での挑戦を有馬に話してもらった。
Interview & Text by 田中亮太
“FALLING”(2022年)
ーー“FALLING”はニューアルバムからのリードソングです。この曲は、前作『REALIZE』で取り組んだ現代R&B的なバンドサウンドを発展させたうえで、ブラジル音楽的な風通しのよさを入れながら、よりウェルメイドに仕上げた楽曲という印象でした。
「『眺め』の制作時点で、従来のロックンロールの演奏には飽きていて、『REALIZE』ではそれを一回捨てて新しいチャレンジをしてみたんだよね。それは、おとぎ話なりの最新のポップミュージックへのアプローチというか、このバンドでディアンジェロの全然ノれない感じの曲をやってみる、みたいな挑戦だった。『REALIZE』はサイケデリックだったり、ちょっとダウナーなソウルっぽかったりしたんだけど、その次は『REALIZE』の手法を使ったうえで、完全無欠のポップアルバムを作りたかった。特に今回の“FALLING”は、それを振り切ってやれた曲だと思う」

ーー『REALIZE』の大半の楽曲も“FALLING”も、メロディーとアンサンブル双方の面でループ構造が肝になっているじゃないですか。これはどのあたりの音楽を参照としていたんでしょう?
「いちばんリファレンスになったのは、スタンディング・オン・ザ・コーナーっていうソランジュの『When I Get Home』にも参加していたNYのバンド。ソランジュからの影響も大きかったかな。自分自身、サン・ラとかモダンジャズとかはずっと好きなんだけど、おとぎ話ではなかなかそういう部分を落とし込めなかった。でもソランジュは〈サン・ラやアリス・コルトレーンを聴いてアルバムを作った〉と隠すことなく言っていて、それにも感動したんだよね。じゃあ有馬も自分が好きなものをもっと出したほうがいいんだなって。それでメンバーにもツアーの移動中にソウルなんかを聴かせて、そういう引き出しを作ってもらった。そのうえで『REALIZE』以降の制作は進めているんだよね」
ーーじゃあ、ある意味でダウナーにも聴こえる『REALIZE』の楽曲と比較して、“FALLING”をポップなものにするためにどんな工夫をしたんですか?
「『REALIZE』のときは、その当時の世界情勢や息苦しいムードをラヴソングとして表したんだけど、今回の“FALLING”は性別も年齢も関係なく、恋をしたことがあるすべての人たちにわかりやすく届けられるものにしたかった。だから、できるだけポップな言葉を羅列していて。そのうえで〈断言しない〉というのがテーマだったかな」
ーー確かにこの曲は〈絶対に〉という言葉を繰り返すことで、意図的に作者の真意を読み取れないようにしている。どうしようもなく恋に落ちてしまう瞬間をロマンティックに歌っているようでもあり、一歩離れた場所から〈恋なんてそんなにいいものではないよ〉とシニカルに見つめているようにも聴こえます。
「そう、限定していないんだよね。聴く人がいまどういう時間を生きているかにかかわらず聴ける曲になっていると思う。たとえば恋をした瞬間だけの曲って、いまそういう状態の人しか聴けなかったりするじゃん? でも、これは恋をしている人も、恋に絶望している人も聴ける。それは基本的に距離を置いたところから歌っているからだと思う。それには自分が離婚したことも関係しているとは思うよ。新作はアルバムを通して、いつ聴いてもいい作品になっているんじゃないかな」
[Download / Streaming]『SALE!』(2007年9月)
ーー『SALE!』が出たときのことはよく覚えています。当時、自分は京都のCDショップで働いていて、同僚にシンガーソングライターのゆーきゃんがいたんですけど、彼が〈銀杏BOYZの峯田(和伸)にフックアップされたバンドだよ〉と教えてくれたんです。そういう位置付けって自分たちではどう思われていました?
「いや、すごい戸惑ったよ。だって、もともとサイケやプログレが好きではじめたバンドだったし、オシリペンペンズとかあふりらんぽとか関西ゼロ世代のバンドと高円寺のU.F.O.CLUBで対バンしていたわけだし。でも、たまたま自分のバイト先にGOING STEADYのファンの子がいて、一緒にライブを観に行ったらすごく良くて。ゆらゆら帝国とかDMBQとかと同じように語られてもいいバンドだなと思った。そのあと、たまたま峯田さんに会えて、練習音源を渡したらブログに書いてくれたんだよね。そんなことになるとは思ってもいなかったから、めちゃくちゃビビった(笑)。で、そのあと対バンすることになったんだけど、当時は10分くらいの曲しかなかったから、5分以内の曲をライヴ前にがんばって量産して。そこからポップミュージックというものは、ちゃんと聴かせないといけないものなんだとわかっていった。銀杏BOYZを好きな人がいる場所に行ったときに、ちゃんとその人たちを楽しませないといけないなと思ったんだよね。だから、峯田さんには感謝してもしきれないよ。あれがなかったらいまがないわけで」

ーー10分くらいの曲ばかりをやっていたバンドが、3分間のポップソングに慣れていくうえで苦労はありました?
「めちゃくちゃあった。それまでは抽象的な言葉の羅列が多くて、人を感動させるような歌詞はいっさい書いてこなかったんだよね。そこはすごい困った。だから、その頃は洋楽の歌詞を自分なりに和訳したような歌詞が多かったかもしれない。レディオヘッドの“High and Dry”や“Creep”の歌詞を勝手にこういうもんだろ、と翻訳したようなものとか」
ーードラマーの前越(啓輔)くんは銀杏BOYZと対バンしたあとにバンドに加わったそうですね。いまとなっては不動の4人という感じですが、当時メンバーが共通して好きだったバンドは?
「その当時はフレーミング・リップスとペイヴメント。それだけだと思う。あと、有馬はR.E.M.が大好きだったから、それも音楽の要素としては入っているかな。その3つだけをとるとまったく銀杏BOYZじゃないんだよね」
ーーなるほど。『SALE!』にはカレッジロック的な側面もあるなと思っていたので、R.E.M.の名前が出てきたのには納得です。彼らの名曲と同名の“NIGHTSWIMMING”という曲も収録されているわけで。
「うん、“NIGHTSWIMMING”のコード進行とかは完全に影響下にある。R.E.M.はいまだに研究しているな。だから、ほぼ洋楽志向だったんだよね」
ーーアルバムにはガレージ/ロックンロール的な面も多く出ていますけど、それはどんな音楽からの影響を反映したものだったんでしょう?
「そもそもTHEE MICHELLE GUN ELEPHANTに憧れて明治学院に入ったような奴らの集まりだから、そういう要素は当たり前にあったんだよね。むしろ最初はホワイト・ストライプスとか(当時のリヴァイヴァル勢)は馬鹿にしていたし、ダムドのほうがかっこいいよねとか言っていたかな。だから、どっちかというとストゥージーズとかオリジナルに寄った音になっていると思う」
ーーそうですね。じゃあファーストアルバムを制作するうえで心掛けていたことは?
「勢いをとらえる、ということかな。勢いのあるアルバムが出来ればいいよねってことしか考えていなかった。当時からブラジルの音楽とかも好きだったから、ベックみたいなことをやりたいとかもホントはあったんだけど、そういう演奏はまだできなかったんだよね」
ーーギターの牛尾(健太)くんが先日開催されたセカンドアルバム『理由なき反抗』のアナログ盤リリース記念ライヴで『理由なき反抗』を〈おとぎ話にとってのオアシス『(What’s the Story) Morning Glory?)』みたいなものだ〉と言っていましたけど、有馬くんがそういう言い方でこのファーストアルバムをたとえるとすれば?
「えーっとね、フレーミング・リップスの『Transmission from the Satellite Heart』かな。“She Don’t Use Jelly”が入っている作品。あのアルバムみたいにポップでノイジーというのもファーストのテーマではあったんだよね。ウィーザーのファーストみたいなものもめざしたかったんだけど、あれは演奏もめちゃくちゃ上手いじゃん。ぼくらは、〈下手なのになんか味がある〉みたいなものを考えていたな」
ーーちなみに当時、仮想敵はいました?
「仮想敵は、それこそレーベルのUK.PROJECTだったり青春パンクだったりだったかな」
ーー高円寺のU.F.O.CLUBを根城にしていたバンドが、いわゆる下北沢のギターバンド・シーンの象徴的なレーベルであるUK.PROJECTからリリースというのも、外から見たときに、おとぎ話の立ち位置をわかりにくくしていた一因でもありましたよね。
「ホントにそうだと思うよ。そもそも下北沢でやっているバンドじゃなかったし、むしろ下北沢ファックという感じで中指を立てているようなバンドだったからね。だから、(リリースにあたって)ホントに自分たちでいいのかなとはすごく思った」
ーーじゃあ、峯田フックアップという点で青春パンクの亜流とも捉えられかねない位置にいるなかで、そこに抗うためにやったことは?
「それはファーストシングルの“KIDS”がバラードってことかな。8ビートのパンクじゃないから、みんなめちゃくちゃびっくりしたと思うし、反旗を翻してやろうという意識もあった。有馬にとっては大事な曲だね」
ーーなるほど。最後に、有馬くんにこのアルバムから当時のバンドを象徴している曲を1曲選んでもらいたいんですけど、やはり“KIDS”?
「それはもう“KIDS”だね。“KIDS”を作らなかったら、おとぎ話は続かなかったと思う。あれはすごくよく出来た曲で、いまの自分でも全然普通に歌えるんだよね」
ーーそれはどうして?
「うーん、わかんないけど、いまも思っていることが変わらないからかな。“KIDS”=ファースト・シングルの時点で自分が死ぬことを歌っているんだよね。だから、その時点で生きていくうえ、音楽を作っていくうえでのテーマのひとつが出来上がっていたんだと思うよ」
[Download / Streaming]—
おとぎ話<OUR VISION>
2022年8月13 日(土)
東京都 日比谷野外大音楽堂
開場 16:00/開演 17:00
チケット:全席指定 ¥6,600(税込)
お問い合わせ: HOT STUFF PROMOTION TEL:03-5720-9999